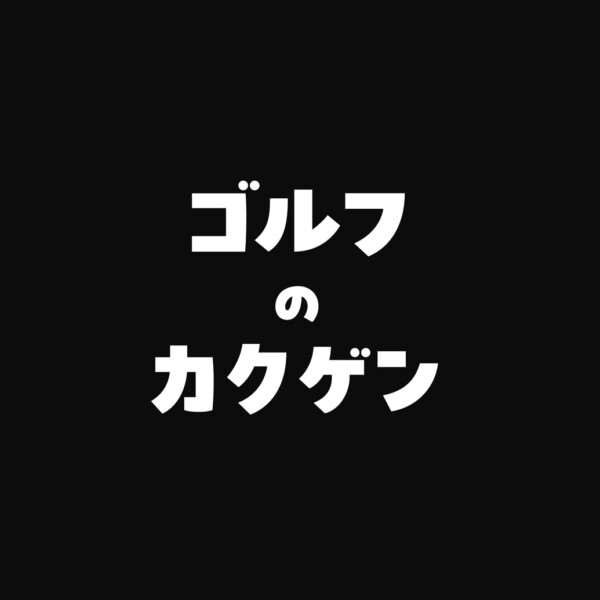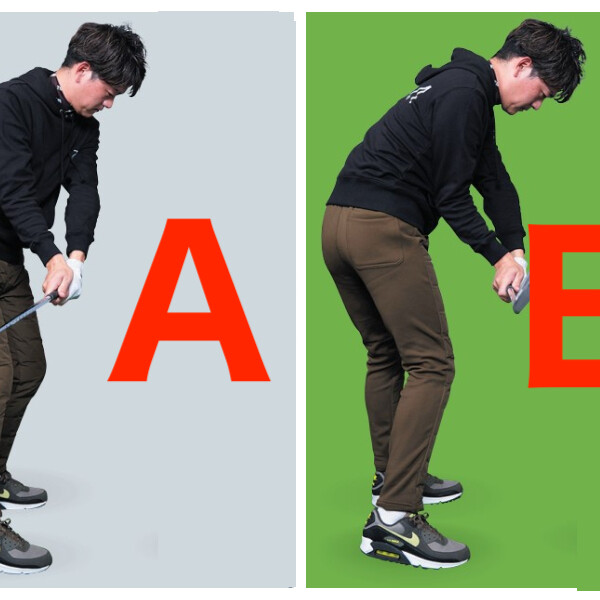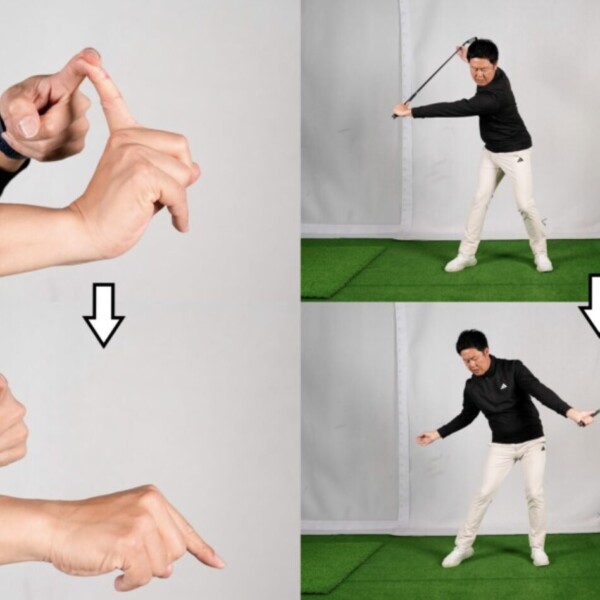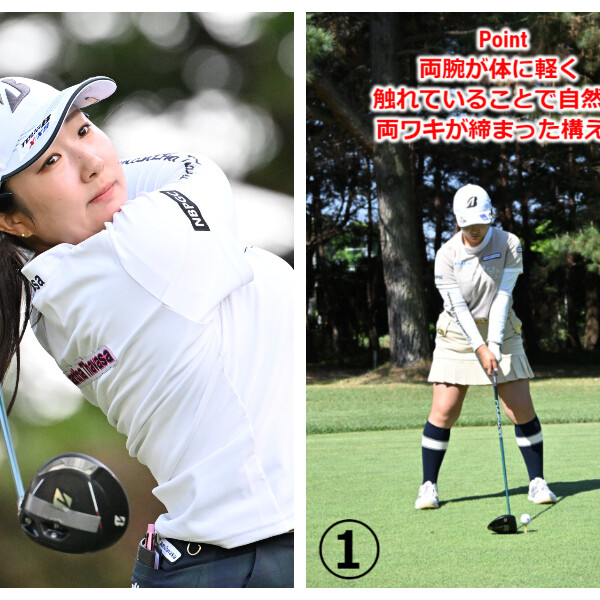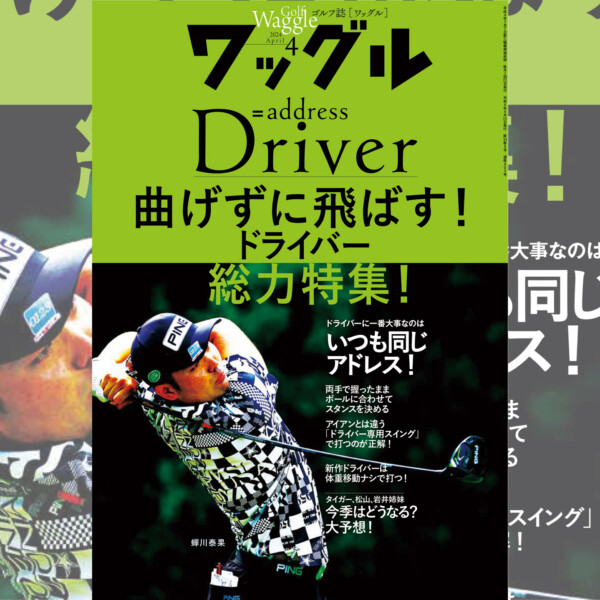欧州勢の強さの秘訣は「米大学ゴルフ」!?
PGAツアーで欧州勢の優勝者が目立っている。
彼らの多くが、アメリカの大学ゴルフ部で腕を磨いた経験がある。
日本人選手もPGAツアーを目指す手段として、これからは、米国の大学でゴルフを経験する道があるのかもしれない
【関連記事】タイゴルフ旅3泊4日で3ラウンド。豪華賞品のコンペも開催!
7試合を終えて米国勢は1人

PGAツアーの2025年シーズンは2月半ばのジェネシス招待までで7試合を終え、7名のチャンピオンのうちの実に4名が欧州出身だった。
PGAツアーの本拠地である米国の出身者は、ファーマーズ・インシュアランス・オープンで優勝したハリス・イングリッシュただ1人。残る2名は、開幕戦のザ・セントリーを制した松山英樹が日本出身、ソニー・オープン・イン・ハワイで優勝したニック・テイラーがカナダ出身という内訳で、過半数が欧州勢という結果には少々驚かされた。
欧州出身の4名のチャンピオンと、その出身国を見てみると、ザ・アメリカン・エキスプレスで勝利したセップ・ストラカはオーストリア出身で、AT&Tペブルビーチ・プロアマの勝者、ローリー・マキロイは北アイルランド出身。WMフェニックス・オープンで勝利したのは、ベルギー出身のトーマス・デトリー。その翌週、ジェネシス招待を見事に制覇したのは、スウェーデン出身のルードビック・アベルグだった。
かつて、米国が拠点のPGAツアーで欧州勢が大活躍していた時代といえば、イングランド出身のニック・ファルド、スコットランド出身のサンディ・ライル、ウエールズ出身のイアン・ウーズナム、スペイン出身のセベ・バレステロスやホセ・マリア・オラサバル、ドイツ出身のベルンハルト・ランガーといった選手たちが輝いていた1980年代から90年代が思い出される。
その後も、英国やスペインといったゴルフ界で「お馴染みの国々」からは、毎年のように強い選手がPGAツアーにやってきている。だが、昨今のPGAツアーには「そこではゴルフが盛んなのですか?」と首を傾げてしまいそうな国からやってくる欧州勢が徐々に増えつつあるのが、傾向といっていい。
アベルグの故郷スウェーデンからは、男子選手ならイエスパー・パーネビックやヘンリック・ステンソン、女子選手ならアニカ・ソレンスタムといった有名選手がすでに輩出されているため、現地のゴルフ事情をよく知らなくても、「きっと、その国ではゴルフが盛んに行われているのだろう」と想像できる。
しかし、オーストリアやベルギーとなると、ゴルフ場はどのぐらいあるのかも、ゴルフ人口が多いのか少ないのかも、ゴルフ人気が高いかどうかも、「見当すらつかない」という方々が大半なのではないだろうか。
しかし今季は欧州のそうした国々からPGAツアーのチャンピオンが着実に生まれている。
オーストリア出身セップ・ストラカ
今季の西海岸シリーズ第1戦、ザ・アメリカン・エキスプレスを制し、PGAツアー通算3勝目を挙げたストラカは、オーストリア出身の31歳。彼はオーストリアで生まれ育ったが、14歳のときに米国南部のジョージア州へ一家で移住。しかし、国籍は変えず、今でもストラカはオーストリア人だ。ジョージア大学ゴルフ部では、双子兄弟のサムとともに活躍。しかし、3年生のときにアプローチ・イップスになり、大学ゴルフ部のチームからは戦力外とみなされたことがあった。
それでも歯を食い縛って努力して、イップスを克服し、2016年にプロ転向。下部ツアーなどを経て、PGAツアーには2019年に辿り着いた。オーストリア人選手がPGAツアー出場資格を獲得したのはストラカが史上初となったが、なかなか成績は上がらず、世界ランキングは200位台と低迷。
しかし、名コーチ、ジョン・ティレリーの門下に入ってからは成績が上向き、2022年ホンダ・クラシックで初優勝、23年ジョンディア・クラシックで2勝目を挙げ、そして今年、ザ・アメリカン・エキスプレスで3勝目を挙げた。
オーストリア人選手がPGAツアーの優勝者になったのも、ストラカが史上初である。
ベルギー出身トーマス・デトリー
アリゾナ州のTPCスコッツデールで開催されたPGAツアーで最も賑やかな大会、WMフェニックス・オープンを制したのは、ベルギー出身の32歳、トーマス・デトリーだった。
この大会の開幕前、米国のブックメーカーが弾き出したデトリーの優勝確率は、わずか0.4%とされていた。その小さな可能性を4日間72ホールで100に変え、初優勝を果たしたデトリーは、PGAツアー史上初のベルギー人チャンピオンとなった。
デトリーはベルギーの首都ブリュッセルで生まれ、大学は米国のイリノイ大学へ留学。2016年のプロ転向後は欧州のチャレンジツアーの大会、ブリヂストン・チャレンジで早々に勝利したが、「僕がプロキャリアにおいて優勝したのは、これまではこのチャレンジツアーの1勝だけだった」。
以後、優勝の二文字からは遠ざかっていたが、東京五輪でもパリ五輪でもベルギー代表選手として戦い、2023年からはPGAツアー参戦を開始。昨年はヒューストン・オープンで2位タイ、全米プロでは4位タイ、今季の開幕戦、ザ・セントリーでも5位タイに食い込むなど、着実に成績を向上させていた。
そして、2度目の出場となった今年のフェニックス・オープンで、ついに念願の初優勝を果たした。
スウェーデン出身ルードビック・アベルグ
大規模な山火事被害の影響で、戦いの舞台がロサンゼルス郊外のリビエラからサンディエゴ郊外のトーリーパインズに変更されて開催された今年のジェネシス招待は、スウェーデン出身の25歳、ルードビック・アベルグが見事な逆転勝利を飾った。
アベルグは、幼少時代はサッカー少年だったが13歳からゴルフを始め、みるみる上達。地元のハイスクールのゴルフ部で活躍していたところ、スウェーデンのナショナルチームに迎えられ、ナショナルハイスクールへ転校。以後、ゴルフのエリート教育を受け、大学は米国のテキサス工科大学へ留学した。
そして、PGAツアー・ユニバーシティでも世界アマチュアゴルフランキングでも1位になり、2023年にプロ転向と同時にPGAツアー出場資格を獲得。
欧州のDPワールドツアーにも出場し、早々にオメガ・ヨーロピアン・マスターズで初優勝した。ライダーカップにも初出場し、大活躍して大型新人ぶりを世界にアピールすると、その直後にはRSMクラシックを制してPGAツアーでも初優勝。
世界ランキングは4位まで上昇し、瞬く間に世界のトッププレーヤーの仲間入りを果たすと、今季はシーズン早々にシグネチャー・イベントのジェネシス招待で通算2勝目を挙げた。
そんなアベルグには「もはやメジャー優勝を実質的に狙える新たなレベルへ昇格した」という大きな期待が寄せられている。
海外で戦うチャレンジ精神
こうして見てみると、今季、PGAツアーで勝利を挙げた欧州勢のうち、すでにトッププレーヤーの地位を確立しているマキロイを除いた3名は、いずれも米国の大学ゴルフを経由していることがわかる。
ストラカはジョージア大学、デトリーはイリノイ大学、アベルグはテキサス工科大学に進み、いずれも、そこでゴルファーとしての将来のための土台を築いたといっていい。
とりわけアベルグは、米国のカレッジゴルファーを対象としているPGAツアー・ユニバ―シティの制度をフル活用し、その恩恵を授かったといえそうである。
PGAツアーやDPワールドツアー、あるいはUSGAやR&Aが若い選手たちの未来のために創設しているさまざまな制度とその恩恵は、ただゴルフが上手ければ、勝手に降ってくるというものではない。
国境を越え、大陸を越え、海を越え、積極的に自ら足を伸ばして世界にチャレンジしない限り、そうしたチャンスは巡っては来ない。
ストラカもデトリーもアベルグも、欧州出身ではあるが、彼らの挑戦の場は、欧州にとどまらず、米国へ、世界へと広がっている。いや、自ら世界へ歩み出すフットワークの良さを持ち合わせているからこそ、彼らはPGAツアーで勝利を掴み取ることができたのだろう。
近年は日本の選手も世界の舞台で奮闘している。久常涼と星野陸也はDPワールドツアー経由でPGAツアーに辿り着き、大西魁斗はPGAツアーの下部ツアーであるコーンフェリーツアー経由で、金谷拓実はPGAツアーのQスクール経由で、それぞれPGAツアーの正式メンバーとなって戦い始めている。彼らも世界へと自ら歩み出した挑戦者たちだ。
だが、これから彼らの後に続こうとしている日本のジュニアや若者たちには、欧州勢のチャンピオンが、いずれも米国の大学ゴルフを経験していることにも、是非とも注目していきただきたいと思う。
欧州勢がそうであるように、日本のゴルファーにも、米国の大学ゴルフ経由でプロになるという道や選択肢、チャンスがある。
いやいや、もっといえば、米国のカレッジゴルファーを対象とするPGAツアー・ユニバーシティという制度に倣い、昨年はDPワールドツアーによって米国以外の大学生やアマチュアを対象とする「グローバル・アマチュア・パスウエイ」という制度も創設されたため、日本の若者は高校卒業後に世界へ歩み出して、チャンスを得る道が、米国と欧州、アジアも含め、世界のあちらこちらで開けているといっていい。
もはやゴルフ界も母国のツアーで経験を積んでから世界へ挑む時代ではなく、実力ある選手、世界のトップを目指す選手は、どんどんグローバルな挑戦を開始している。そのための制度も次々に整備され、挑戦者たちを後押ししてくれている。
その一方で、米国の若いゴルファーが米国以外の国へゴルフ留学する例は、昔も今も決して多くはない。米国は、ジュニアやアマチュア、カレッジゴルファーを支援する制度が国内にたくさんあるサンクチュアリーであるせいか、米国のゴルファーは米国に留まる傾向が強く見られるといえるのかもしれない。
しかし、その殻を破るかのように、米国から欧州へ渡り、海外修行を積んだ上で米国に戻って成功した選手もおり、真っ先に思い浮かぶのは、メジャー5勝のブルックス・ケプカだ。
ケプカはフロリダ州立大学を卒業してプロ転向。「どうせ何も無いなら、米欧どちらから挑戦してもいいわけだし、欧州のほうが大自然の影響を大きく受けるリンクスゴルフで揉まれることで自分を早く強く磨けると思った」とのことで、そのまま欧州へ渡り、チャレンジツアーで次々に4勝を挙げて、欧州ツアー(現DPワールドツアー)へ昇格した。
そして、欧州で初優勝して足場を固め、その後にスポット参戦でPGAツアーに挑み始め、あっという間にメンバーシップを手に入れた。
見知らぬ土地、不慣れな環境に身を置いて戦う日々は、必ずや選手を強くする。リブゴルフに移籍後もケプカの強さがいまなお翳らないのは、若い時代の欧州転戦の日々を経て、彼にそういう強さが備わっているからに違いない。
だが、ケプカのように「逆輸入型」で成長した米国出身選手は決して多くはなく、そうした傾向が、今季の序盤戦7試合で米国人優勝者はたったの1人という惨憺たる結果に結びついているのではないだろうか。
もっともっと世界へ踏み出そう――グローバル化が進んでいるゴルフ界で今、最も求められているのは、そういう積極姿勢とチャレンジ精神である。

いかがでしたか? 世界で活躍する日本人プレイヤーが増えることを期待しましょう。
文=舩越園子(ゴルフジャーナリスト)
写真= AP/アフロ
【あわせて読みたい】
石井忍、石井良介、岩男健一……名コーチと名コースで上達できるイベント!
7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説